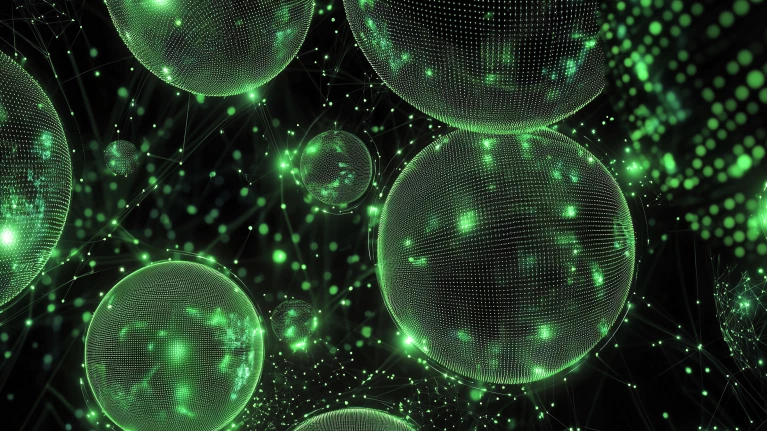AIはもはや遠い将来の話ではない。経営層や管理職は、すでに日々の業務にAIを取り入れている。しかし一般従業員の間では、このテクノロジーはいまだ十分には受け入れられていない。
経営層、管理職の4分の3以上が、生成AIを週に数回以上使用していると回答した一方で、一般従業員ではこの割合は51%と伸び悩んでいる。
利用率に差が生じている一方、AIの進化は加速している。多くの企業は、既存業務のなかにAIツールを単に導入するだけでは、AIに潜在する可能性を十分に引き出せないことに気づき始めている。AI活用の真価は、企業がさらに一歩踏み込み、業務フロー全体をエンドツーエンドで再設計してはじめて発揮される。
金融サービスやテクノロジー業界を筆頭に、調査に回答した企業の半数が、生産性向上を目的とした導入フェーズ(Deploy)から業務フローの再設計フェーズ(Reshape)へと移行しつつある。
これらの見解は、BCGが毎年実施している「職場におけるAI活用に関する意識調査」に基づいている。今年の調査は世界11の国・地域で働く1万600人以上の経営層、管理職、一般従業員を対象に行われた。調査結果の詳細は、以下のスライド資料で紹介している。
一般従業員のAI活用をどう促進するか
企業が業務フローを再設計するためには、一般従業員による主体的な関与が不可欠だ。調査では、一般従業員のAI利用率の伸び悩みを打開するために企業が取り得る方策を提示している。
- 経営層からの支援。経営層が明確な支援を示すことで、一般従業員はAIを日常的に利用する可能性が高まり、仕事の満足度向上やキャリアに対する前向きな意識の醸成にもつながる。例えば経営層のサポートがある場合、「生成AIによって仕事が楽しくなる」と考える一般従業員の割合は55%に達した(サポートがない場合は15%)。しかし、そうした支援を受けていると答えた一般従業員は約4分の1にとどまっている。
- 適切なツールの提供。必要なAIツールが会社から提供されない場合、調査回答者の過半数が代替手段を見つけて独自に使用すると答えている。こうした状況は不満の高まりやセキュリティリスク、組織的な取り組みの分断につながりかねない。
- 十分なトレーニングの実施。企業がトレーニングを実施するとAIの日常的な利用率は高まり、AIに対する信頼感も高まる。特に、対面かつコーチから助言を受けられる形式で5時間以上トレーニングを受けた場合に、日常的な利用率が著しく高い。しかし、十分なトレーニングを受けたと回答した人は全体の約3分の1にとどまっている。
業務フローの再設計がもたらす価値
AIを活用して業務フローを積極的に再設計している企業は、価値創出につながるさまざまな恩恵を得ている。こうした企業で働く人は、AIの導入が進んでいない企業で働く人に比べて、業務時間を大幅に節約している。さらに、意思決定の精度が向上し、より戦略的な仕事に携わるようになっている。
こうした成果は偶然に生まれるものではない。再設計フェーズにある企業は、AIによって創出された価値を的確に追跡・把握している。そうした企業はトレーニングにも多くの時間を割いており、「経営層からサポートされている」と回答した人の割合が高い。
しかし、この再設計には課題もある。AIを中心に据えて全社的に業務フローの再設計を進めている企業で働く人は、そうでない企業で働く人と比べて、雇用の安定に対し不安を抱く傾向にある(46%対34%)。また、今後10年で職を失う不安を感じている人の割合は、一般従業員(36%)よりも経営層・管理職(43%)の方が高い。こうした不安を和らげる施策は今後も継続して行う必要があり、トレーニングの実施やアップスキリングの支援が重要になる。
AIエージェントの可能性――実装は道半ば
AIエージェント(学習・推論能力を備え、複雑なタスクを自律的にこなすデジタルアシスタント)が、大きな注目を集めている。しかし調査結果によると、このツールはまだ黎明期にあるようだ。「AIエージェントが自社の業務フローに統合されている」とした回答者はわずか13%にとどまり、その働きを理解していると答えた人も3分の1にすぎない。
AIエージェントについて十分な情報を得て理解を深めると、不安は関心や期待へと変わっていく。AIエージェントを脅威としてではなく、自身の業務を支援する協働パートナーとして捉えるようになるのである。
職場におけるAI活用、次の展開は
今回の調査結果は、企業におけるAIの導入・統合が進んでいることを示している。一方で、とりわけ雇用の安定に対する懸念も浮き彫りとなった。昨年の結果と同様、AIを使用するほどに仕事を失う不安を抱く傾向が見られる。こうした現象は、蒸気から電力への移行など過去の技術革新の際にも起きており、よく知られた課題である。
AIの導入から価値創出に至るまでの道のりは、本質的には人と機械の協働のあり方を再構築するプロセスである。この変革に真剣に取り組む企業は、AI活用の真価が、より洗練された働き方の実現にあることを理解している。適切に行えば、その企業で働く人々はただAIを使うようになるだけでなく、自己の能力をさらに発揮して成長できる。企業は、次のような取り組みからスタートするのが望ましい。
- トレーニングの重要性を軽視しない。必要な投資・時間・経営層の支援を、責任をもって提供する。
- AI活用によって生み出された価値を、生産性・仕事の精度・従業員満足度などの指標で的確に追跡・把握する。
- 業務フローを再設計し、AI活用の価値を引き出すために、人材に投資する。AIが仕事、従業員、働き手全体に与える影響を予測する。人材を適切に再配置するために、アップスキリングとリスキリングの仕組みを構築する。
- 経験曲線を加速させるために、AIエージェントを用いた徹底的な実験を行う。A/Bテストを通じて、その効果と潜在的なリスクを検証・測定する。